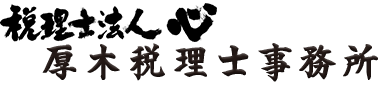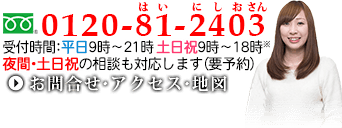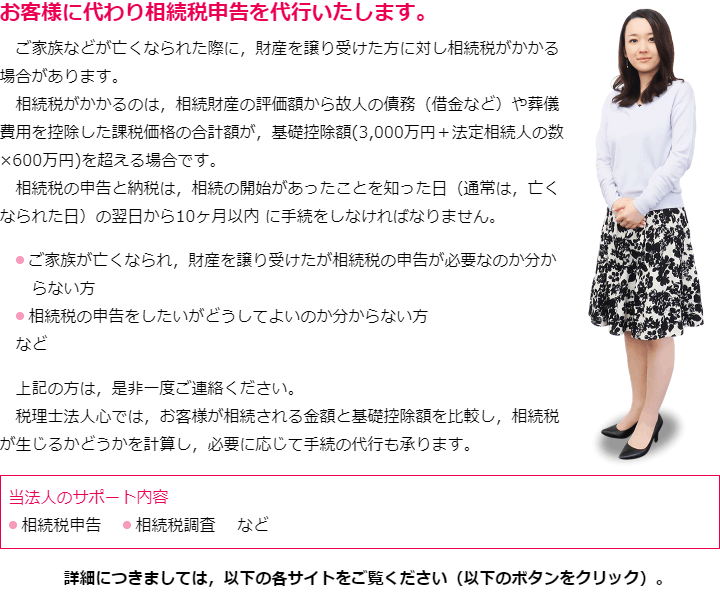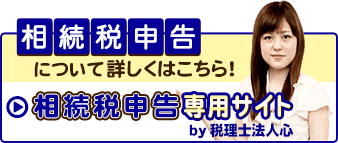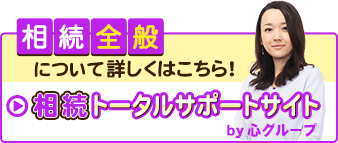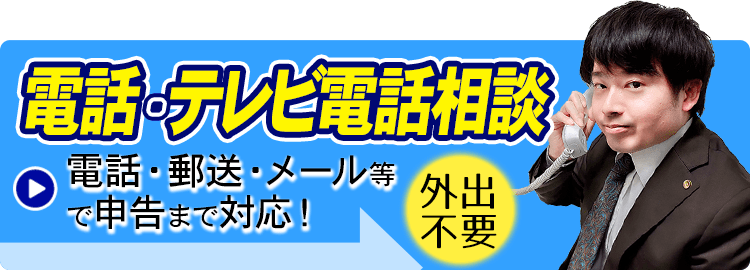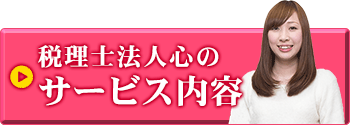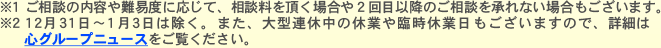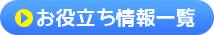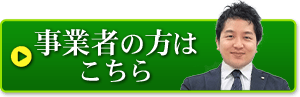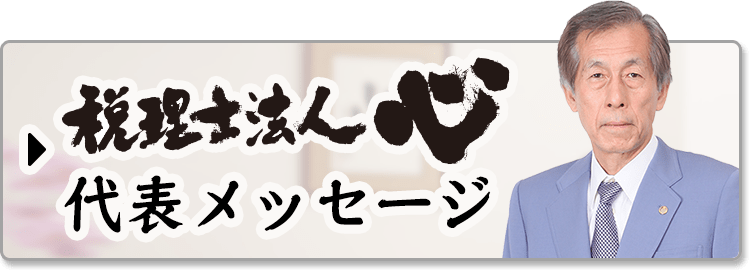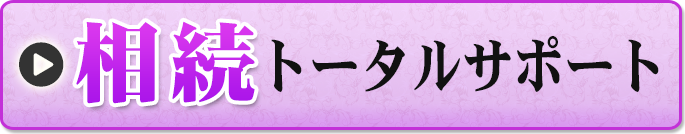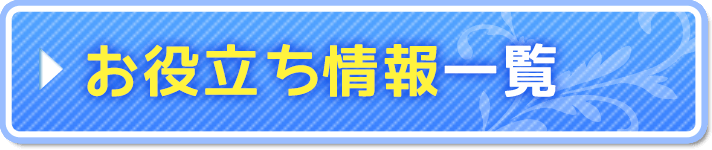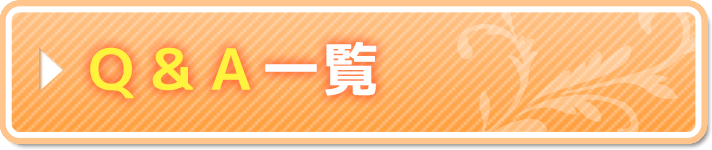相続税申告(相続発生後)
相続税の対象となる財産・ならない財産
1 相続税の課税対象となる財産の概要

原則として、被相続人に属していた財産は、すべて相続税の課税対象になります。
政策的な観点等から課税すべきでないものについては、例外的に課税対象から外れるという扱いになっています。
課税対象となる財産の代表的なものとして、次のものが挙げられます。
①現金・預貯金
②有価証券(上場株式、投資信託など)
③不動産
民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上は課税対象となる「みなし相続財産」にも注意が必要です。
みなし相続財産の典型としては、次のものが挙げられます。
④生命保険金、死亡退職金
また、相続開始前3年以内の贈与(令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内)により取得した財産も相続税の対象となるほか、相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産(一部例外があります)も課税対象です。
以下、①~④の財産、および相続税の対象にならない財産について説明します。
2 相続税の対象となる財産について
⑴ 現金・預貯金
現金と預貯金は、相続開始時点の残高が課税対象となりますので、通帳や金庫などを確認します。
定期預金がある場合、相続開始時点までに発生していた既経過利息も課税対象になります。
⑵ 有価証券(上場株式、投資信託など)
上場株式や投資信託などは、一定の評価方法に基づいて評価額を算定します。
証券会社や金融機関によっては、残高証明書を取得する際、相続税評価額を記載したものを提供してくれることもあります。
⑶ 不動産
被相続人の土地や建物も課税対象となります。
建物は、固定資産評価額が評価額となります。
土地は、路線価地域のものは、1㎡あたりの路線価に敷地面積を掛け合わせ、土地の形状等に応じた補正を行って評価額を算定します。
倍率地域にある土地については、固定資産評価額と倍率表を用いて評価額を算定します。
⑷ 生命保険金、死亡退職金
生命保険金、死亡退職金は、相続税においては相続財産とみなして申告が必要となります。
評価額は、保険会社や被相続人の勤務先から取得した資料をもとに算定します。
なお、生命保険金や死亡退職金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
3 相続税の対象にならない財産について
⑴墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているもの。
ただし、骨とう品など財産的価値が高いものや、被相続人の事業用の商品であったものは相続税の対象となります。
⑵宗教、慈善、学術など公益目的事業を行う個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、かつ公益目的事業に使われることが確実なもの。
⑶地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する、心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利。
⑷被相続人が経営していた幼稚園の事業に使われていた財産で、一定の要件を満たすもの。
相続人のいずれかが、その幼稚園の経営を継続することが条件となります。
⑸相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの。相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。